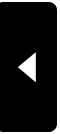2010年05月08日
羽アリ

庭木に発生した羽アリです。
この他、玄関ドア枠からの発生などありました。
シロアリフォーラムの先輩方からは
もう少し早い時期から情報を頂いていましたが、
私の周りではGW後半が最初でした。
地元のシロアリ仲間もそうだったようで
「全然羽アリでないね」と話していました。
変な気候が原因でしょうか。
写真のような家から離れた場所での羽アリは
気にする必要はありません。
むしろいて当たり前です。
家から発生した場合は、あせって殺虫剤をかけたりせず、
信頼できる専門家にじっくり見てもらいましょう。
2010年04月06日
増改築
最近、増改築の仕事が多い。
そんな現場では新築や既築より目につく場所が多い。
もともと土だった床下にコンクリートが流された為
束などの木部が埋まってしまっていたり
店舗や玄関だった場所のタイルが残されたままだったり
増設された基礎やブロックの継ぎ手が目立ったり
床下そのものが、後々点検不可能な高さだったり
見出すとまだまだ出てくる。
そしてよく言われるのが「たくさん薬を撒いておいてくれ」です。
私の技術ではそうせざるを得ない場合も多々ありますが
状況の改善で「たくさん」は必要でない場合が多いものです。
私がもっと早い段階で現場にかかわれるよう努力しなければなりません。
そんな現場では新築や既築より目につく場所が多い。
もともと土だった床下にコンクリートが流された為
束などの木部が埋まってしまっていたり
店舗や玄関だった場所のタイルが残されたままだったり
増設された基礎やブロックの継ぎ手が目立ったり
床下そのものが、後々点検不可能な高さだったり
見出すとまだまだ出てくる。
そしてよく言われるのが「たくさん薬を撒いておいてくれ」です。
私の技術ではそうせざるを得ない場合も多々ありますが
状況の改善で「たくさん」は必要でない場合が多いものです。
私がもっと早い段階で現場にかかわれるよう努力しなければなりません。
2010年03月04日
木クズとシロアリ
建築時に床下に残された残材の様子です。
複数の蟻道が確認できます。
シロアリの動きがある床下では
このような残材は餌となってしまいます。
調査時に残材などのゴミはすべて撤去してきますが
よくお客様が「そんな事までやってくれるのか」と驚かれます。
しかし、要因を取り除くのもシロアリ対策の一つになるのです。
2010年02月22日
無意味な穿孔
現場では、たびたび意味の無い穿孔(ドリルで木に穴をあける事)を見かけます。
この現場では、かよわい蟻道の近くで、
根太掛けや根太に無闇に穴をあけられています。
はっきり言って薬剤は入りません。
※この現場は穿孔すら必要ではありません。
被害の状態をしっかりと見て、なるべく小さく、
一つでも少ない穿孔で被害材内部に薬剤を届けるのが
シロアリ屋の仕事だと思うのですが・・・。
これではシロアリより、ドリルによるダメージの方が大きいです。
予防工事でもこんな風景がたまにあります。
シロアリの被害も何もない土台などに等間隔で穴をあけ、
薬剤を注入するという穿孔処理法・・・。
見ると悲しくなってきます。
何も知らないお客様から見ると、非常に丁寧に見えるようですが
効果やダメージを考えれば、あんな無意味な処理はありません。
もう一度書きますが、シロアリよりドリルによるダメージの方が大きいです。
2010年02月06日
外部からの蟻道
基礎外部からのばされた蟻道です。
こういった侵入は多いものです。
このような場合、床下がコンクリートだろうが
主要材が鉄骨だろうが関係ありません。
どんな住宅でも必ず木材が使われていますし
和室の畳や押し入れに被害が出ることも少なくありません。
シロアリが侵入しにくい構造でも
外部にしっかり目を配る事が大切です。
2010年01月26日
配線モール
基礎外周に張り付いている配線モールです。
シロアリの対策では床下ばかりに目が行きがちですが、
このような個所を見逃してはいけません。
この中はシロアリの通路となる事があります。
もちろんパッと見ただけではわかりませんので
注意深く調査し確認する事が大事です。
2010年01月18日
配管周り
床下配管周りの写真です。
現在はシロアリの兆候はありません。
この部分だけ土になっていますが
それも大きな問題ではありません。
考えなければならないのは、配管は必ず外から引き込まれていますので
それを利用し、配管づたいにシロアリが侵入する事があるという事です。
そうした場合、たとえコンクリートでもわずかなクラックから侵入する場合もあります。
床下が土だから、コンクリートだからという事だけににとらわれてはいけません。
2009年12月20日
空中蟻道
規模は小さいですが、変化も何もない空中に構築された
空中蟻道の写真です。
活性が高かったのか、それとも
他の何らかの理由があるのかはわかりませんが
この現場の様子では、活性が高かったのが理由かなと思います。
たまにこのような蟻道に出会うのですが
普通に蟻道を作った方が簡単そうなのにと思ってしまいます。
もしもシロアリと話ができるものなら
「なぜ?」と聞いてみたいですね。
案外、「へー、そうなんだ」みたいな理由があるのかもしれませんね。
2009年12月17日
玄関外側
玄関入口脇の写真です。
玄関はシロアリの侵入しやすい個所ですが
この場合は特に注意が必要です。
基礎が外壁に隠され、地に埋まっている状態です。
シロアリは外敵や日光にさらされる事もなく
容易に侵入する事が出来ます。
特に最近は、発泡系の断熱材が使用されますので
そちらに侵入のあった場合には活性も高まります。
幸い被害はありませんでしたので最低限の処理で済みました。
よくお客様に、あんたは外まで見てくれるんだねと言われます。
よくよく話を聞くと、他の業者は床下しかやってなかったとの話をされます。
しかし外回りというものは結構侵入ポイントがあるものです。
なるべく家に傷をつけず、考えながら薬剤を使用すれば
床下より、外に時間がかかることも多いものです。
2009年12月13日
見えない侵入
浴室の柱と外壁付近の写真です。
基礎や外回りには蟻道などの兆候はありませんが
断熱材をずらしてみると、被害痕が確認できます。
これは浴室内部方面からの侵入です。
タイル張りの浴室は、蟻道もないのに被害が出る場所として
よくあることですが、最近はユニットバスの普及により
このような被害は減っています。
しかし、これによく似た条件を持つのが玄関や裏口にあたります。
他より地面と土台が近く、タイルの裏から侵入されれば
床下ではなんの兆候がなくとも被害は進行していきます。
特に玄関ドア枠に木材を使用しており、その枠を
地面に埋め込んでいる場合は注意が必要です。
蟻道の構築云々の前に餌と遭遇できるも同然です。
2009年11月27日
変化のある場所
蟻道の写真です。
地面は粗いですがコンクリートになっております。
コンクリートでもクラックがあれば白蟻は難なく侵入してきます。
そして、変化のある場所に被害は集中します。
わかりにくいですが基礎の角、そして角でなくとも
土台に変化のある場所に一直線に向かっております。
変化のある個所は、白蟻にとっては好都合な場所になってしまうのです。
2009年10月31日
梁の被害
ヤマトシロアリによる天井裏の梁の被害です。
ヤマトシロアリは、イエシロアリに比べると、
比較的小規模な被害が多く、土台や床組み材に被害は多く見られます。
しかし、水の確保が容易だと、集団も大きくなりやすいのか、
高い場所まで被害を及ぼします。
そして被害の程度も大きなものとなってきます。
この現場の場合も、浴室から少しづつ水が浸みていました。
よく、ベランダや2階窓の枠の劣化から、水染みがおこり、
ヤマトシロアリが高い場所で被害を出す事がありますが
早期に発見し原因を断つ事が予防の第一歩につながります。
2009年10月30日
注意したい裏口
裏口の階段付近です。
階段が土台部分を超え結構高い位置まで来ています。
基礎と階段は、コンクリートの打つ時期も違うため、
必ず隙間ができます。
その隙間がシロアリにとっては好都合で、
ダイレクトに土台や壁内柱に侵入できます。
また、基礎仕上げのモルタルに割れが見られますが、
これがひどくなり、モルタルが浮いた状態になると
基礎とモルタルの間もシロアリは侵入してきます。
簡単に目視できる状態ではないので
しっかりと注意していきたい個所です。
※濡れているのは水です。薬剤ではありません。
2009年10月27日
玄関ポーチ裏
基礎パッキンの玄関ポーチ裏の土台付近です。
基礎構造はベタ基礎でシロアリは上がりにくい構造です。
しかし、よく見れば土台の奥はコンクリートが見えており、
ポーチ部分は土台より高い位置までタイルに覆われています。
シロアリは床下からではなく、ポーチ部分から、
大した蟻道の構築もなく床組み材に進入できます。
土台下部は加圧注入材を使用していますので、それ自体の被害は
あまり心配ありませんが、侵入を阻止することはできません。
侵入すれば加圧注入材を通過し、他の床組み材、壁内柱などに被害を出していきます。
この状態はシロアリ対策上、好ましくはありません。
2009年10月22日
防蟻シート
床下に防蟻シートが敷いてあります。
しかしこの状況は、ただ敷いただけで
防蟻に対する効果はありません。
防蟻シートにもマニュアルはありますが、
机の上で出来たようなマニュアルです。
シートを敷き、床がふさがるまでは、いろいろな業者が上を歩き
作業しますので、多少動いても問題ないように、
しっかりと考えながら敷きこんだり、石などが多く
破れやすいと判断した場合などはしっかり地面をならしてから
敷き込むなどいろいろな配慮が必要となってきます。
2009年10月09日
免許更新
今日は、しろあり防除施工士の更新のため
名古屋まで行ってきました。
東名の集中工事が気にはなりましたが
車で行ってみると渋滞に合う事もなくラッキーでした。
3年に一回の更新ですが、毎回思う事、
もっと近くでやってくれ・・・。
2009年10月02日
原因改善
床下のカビの様子です。
少々湿気があり、カビが生えていると、
すぐに床下換気扇や調湿材を薦める業者があります。
しかし、原因を考えればそのようなものは必要ない場合があります。
この現場の場合は、お風呂場のタイルに出来たクラックから
少しずつ水が浸みていた事が原因と思われました。
改築工事と同時進行だったため、原因部分の補修で充分と判断しましたが
約2ヶ月たち、カビは一切見られなくなりました。
換気扇という余分な商品が必要でなくなり、お客様にも満足していただけました。
2009年09月02日
新築工事より
新築の玄関部分に配管があります。
防湿コンクリートでは、基礎周りのクラックからの
シロアリの侵入がありますが、このような部分は
特に気をつけなければなりません。
また、この後どのような期間でどのように現場が進んでいくか、
コンクリートに対し、どのような薬剤を選択するかなど
その場に合った施工を考えなければなりません。
いろいろなタイプの薬剤がありますが
選択を間違えると効果が発揮されない場合があるのです。
2009年08月27日
床下点検
床下点検の写真です。
地面は防湿コンクリートですが
基礎とは時期がずれてコンクリートが打たれる為、
クラック(隙間、割れ目)が出てきます。
そこに、このように基礎に張り付くような
束や束石部分は、シロアリの侵入しやすいポイントとなります。
一ヶ所一ヶ所、束の裏まで丹念に見て来る事が重要です。
2009年08月21日
土台付近
新築時の土台付近です。
土台には加圧注入材が使用されていますが
和室などはこのように何の処理もされていない木材を背負わせる場合があります。
シロアリの侵入があった場合は、無処理の材に被害が集中したり、
加圧注入材と無処理材の間などに被害を出します。
また、発砲系の断熱材が使用されればそちらにも生息範囲を広げていきます。
新築工事は施工基準に従わなければならない事が多いですが
少しでも考えながら作業すれば、ただ闇雲に薬剤を使用した時と比べ
大きく差が出るものだと思います。