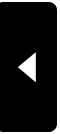2011年07月24日
床下以外
玄関上がり框下の写真です。
穿孔穴、ノズル先端ともに私の持っている
一番細いもの(売ってはいません)で処理しています。
この処理はどこででもするものではなく
詳細な調査、タイルの付け方を把握したうえで行っています。
自分が薬剤をどういう状態でイメージ通りに届けたいかを納得するまで考え、
圧力調整をしながら、大概は床下以上の時間をかけ施工します。
よく、めずらしそうに見ているお客様が
「前の業者はそこまでしてくれなかった」とか
「ただ薬剤を撒くだけではないんだ」と言います。
見える所に撒くだけ、マニュアル施工なんかは誰でも出来ます。
しっかり考えてその場に合った薬剤と処理を行うのが自分達の仕事です。
2011年07月17日
イエシロアリ点検
十年近く前にイエシロアリの駆除をした現場に点検に行きました。
結果は良好です。
当時、天井裏に入り梁を叩くと
カチカチと
兵蟻が威嚇する音が聞こえました。
一緒に入った防除士S.Oさんと
「いるね」
と言っていた矢先、四方八方から
カチ・・・ カチカチ・・・
カチカチカチ!!
か、囲まれた!!!
みたいな勢いでした。
たぶん(;´ д ` )こんな顔していたはずです。
なんとか駆除はしましたが
今お互いに知恵を出したら
全く違う駆除法をするんだろうなと思います。
しかし、防除士Y.Mさんの話では
この近所で毎年羽アリが出て、そのたび業者が来る現場があるらしい。
何たらワンワンとか既に????万とか・・・。
シロアリではなく結果が恐ろしすぎです。
2011年07月10日
ネバダオオシロアリ
ネバダオオシロアリ飼育ケース内です。
生息していた木材の手前に水を含ませたスポンジ、
左に新しい木材を置いておきました。
土壌とはあまり関係の無い種のようですが
見事に糞による蟻道で二つをつなげました。
スポンジに向かっては水取り蟻道では・・・。
乾いた木材も蟻道がつく前に木口をかじって孔開けてましたし
水さえどこかからか取れれば良さそう。
これは一般住宅も危なそうですね。
2011年05月27日
思い出した
こんな穴のあいた現場があった。
これを見た時に12㎜ものドリルで、
被害もない木に穿孔している作業員と話した時の事を思い出した。
なんでそんな事をするの?
加圧注入材の断面写真を持っていた作業員は
加圧注入材ですら表面しか浸み込まないから
こうやって芯に浸み込ませるんだ
ほ、本気でそう思ってるの!?
薬剤は入るわけもなく
その人の顔にはよく薬剤が飛んでくるようです。
また、穴をあけていると蟻道の無い被害を
たまに見つける事があると言い出した。
勉強しなおしてくれ・・・。
2011年02月22日
施工後も注意する
新築での基礎外側の写真です。
寺院のため石造りの階段が土台部分まで置かれています。
一般的な防蟻工事では、床張り前に施工をして完了となりますので
基礎の周りには階段などの付属物が無い状態がほとんどです。
しかし施工後も現場に顔を出していると
通常の施工なんかよりも注意しなければならない個所が必ず出来てきます。
2011年01月24日
床下の無い現場
店舗床の写真です。
床下は転がし根太に床張りで入ることはできません。
このような現場ではちょっとした所から
少しでも情報を得ようとします。
こんな配管周りも案外役に立ってくれます。
そしてあとはイメージが頼りです。
目視できない部分のどこにどのように薬剤を付けたいか、
どうすれば予測通りに薬剤がまわってくれるか、
それにはどの様な道具が必要か、
それを常に考えながら仕事が出来るので
店舗のような現場は非常に面白いです。
2010年12月24日
床の高さ
床下の通気口付近です。
ここは床高も十分で、通気口も高さ22cm位あり非常に作業しやすい現場です。
どこの現場もこの位の通気口と床高があればと思います。
シロアリ屋にとって、床下でのほんの数センチはかなり重要です。
たとえ5mmでも通過に支障が出る場合もあります。
20代前半位までは、小さい通気口や低い床下に入るのを競いました。
中には「お前は猫か!!」みたいな人もいます。
一番すごいので高さ16cmの通気口を通過できる猛者もいました。
しかしそんなことを競い続けるといつか痛い目を見ます。
胸部がはまってしまい身動きもでずパニックをおこします。
また、低い所は息を吐き胸の厚さを無くしながら入りますので
はまってしまうと胸が圧迫され息がうまくできません。
苦しさにマスクを取れば砂埃で余計に苦しく、咳込めば圧迫で胸骨に激痛、
もちろんそんな床の低い場所では仲間がいても引っ張り出せる訳もなく
床を剥いで助けてもらうか、その場で恐怖を抑えつけ自力でなんとか脱出するしかないのです。
その怖さを味わい転職した人もいると聞いた事があります。
もちろん私もはまりました。叫ぶ寸前で自力脱出でした(笑)
今でも低い床下や小さい通気口を見ると怖くて仕方ありません。
2010年12月03日
外部侵入
住宅の基礎にブロック壁がギリギリに設置されています。
見栄えもよく作られた為、水切りの下の僅かな部分も
ピッタリふさがれています。
しかしこれはシロアリには丁度よい進入経路になってしまします。
そして右に見える基礎面のタイル裏も同じ様な事が起こりえます。
床下に蟻道はなくてもこのような場所から被害が発生したりします。
2010年10月02日
イエシロアリ駆除現場
以前ここに書いたイエシロアリの駆除現場です。
大分期間が開いてしまいましたが
シロアリの状態を確認しに行きました。
8本程度あった蟻道や生息部分を見たところ
1本の蟻道を残し生息は確認されませんでした。
巣の特定はできませんでしたが
各所でシロアリの死骸が見られ
玄関内断熱部分もシロアリの動きが無くなりました。
生息があった1本の蟻道は違う系統なのかもしれません。
その部分の処理をしましたので次回で駆除が完了出来ればと思っております。
今の所、薬剤は1リットル程度と粉剤数吹きで済んでいます。
2010年09月28日
修復されている蟻道
温泉施設調査時の写真です。
温泉に接している土台に向かいヤマトシロアリの蟻道が伸びています。
この部分の土台はある程度しっかりしていますが
水染みにより腐朽し土台がほぼ無くなってしまっている所もあります。
地面は防湿コンクリートが打たれていますが
温水管の影響か、非常に暖かくなっておりました。
蟻道が途中から黒く変色していますが、これは水分ではありません。
地面に落ちている蟻道の残骸や曲がりくねった形から考えると
何かしらの影響で何度か崩れているのではないかと推測しました。
温度や水の供給、コンクリートによる密閉など
よい条件が重なりこの場を放棄することなく
修復を重ね固く強い蟻道を作ったのではないかと思います。
2010年09月19日
現場フォーラム
9/17、18日とシロアリフォーラム現場研修会が開かれました。
設計士さんからシロアリ関連の各専門家、研究者さんなど
20人以上が愛知県のイエシロアリ被害現場に入り
宿泊先では深夜まで熱い討論会が行われました。
全国各地から集まった本物の技術者なだけに
非常にレベルが高く核心をついた話ばかりです。
とても有意義でよい意味で緊張感のある二日間でした。
しかし、デジカメを忘れたアホな私でした・・・。
設計士さんからシロアリ関連の各専門家、研究者さんなど
20人以上が愛知県のイエシロアリ被害現場に入り
宿泊先では深夜まで熱い討論会が行われました。
全国各地から集まった本物の技術者なだけに
非常にレベルが高く核心をついた話ばかりです。
とても有意義でよい意味で緊張感のある二日間でした。
しかし、デジカメを忘れたアホな私でした・・・。
2010年09月09日
断熱工法
床下基礎面の断熱材です。
水周りが独立、そこのみ内断熱工法となっています。
配管周りや水抜き穴を確認すると
シロアリは容易に侵入できる状態となっていました。
断熱材にシロアリが侵入すると非常に厄介です。
本当は全部剥がしてしまいたいのですが
住宅の仕様となっている為なかなかそこまでの許可は出ません。
侵入させない為の最小限の撤去をする事で了解を得ました。
新築でも外断熱、内断熱が多くなっていますが
ただ単に薬剤を使用しても断熱材への侵入は防げません。
また、小規模な被害である事が多いヤマトシロアリでも
侵入すると予想以上の被害となったり
習性上、イエシロアリよりも難しい駆除となる現場が
どんどん増えていく事が容易に想像できます。
そして、問題なのが保証書です。
新築時、既築時ともに何の対策もせずにマニュアル施工をし
その結果断熱材に侵入があった場合
間違いなく保険は使用不可能と判断される事でしょう。
まともな防除業者は何かしら住宅メーカーへの説明や
出来る範囲での対策を考え、また実行しているでしょうが
住宅の設計、仕様の問題というのは結構ハードルが高く
なかなか思うようにいかないのも現状です。
薬剤屋さんとも話しましたが、簡単なようですんなりいかない
なかなか大変な問題です。
2010年08月10日
配管部分からの被害
基礎外側を掘った写真です。
トンネルのような穴は外部から配管を通している穴です。
そして明らかに周りとは違う色の土が見られます。
この中はイエシロアリが自由に行き来しており
床下に数本の蟻道を延ばし2階まで被害を出しています。
イエシロアリの生息する地域では駆除後も被害が止まらず
毎年のように防蟻業者が出入りしている現場も見聞きします。
それはマニュアル的に薬剤を散布するが故の結果です。
どこからどのように侵入しているかをしっかり調査しなければ
被害を止めることはできません。
2010年08月01日
イエシロアリ駆除
イエシロアリの駆除処理を行った現場の写真です。
異常行動をおこしたシロアリが地面上に積っています。
しかし想像外の場所でこれが確認されました。
床板に発泡系断熱材が貼り付けられ一体化した構造のため
断熱材内部の食害を注意深く確認していましたが本当厄介です。
シロアリの動きが非常に探りづらく
「なぜここで?」と考え込んでしまいました。
危うく見逃すところを薬剤メーカーさんが見つけてくれて助かりました。
二つの集団からの侵入と考えていましたが一つは他の状況からも駆除出来た模様です。
あとはもう一つの集団に対する処理結果が楽しみです。
2010年07月17日
基礎周り
基礎外周の一部を少し掘った写真です。
真ん中辺りに茶色いものが見えますが
これは基礎作成時の金具です。
錆びて茶色くなっています。
この部分をよく見ると
金具が腐食し出来た隙間にイエシロアリが侵入しています。
この真裏の床下では蟻道が構築され
被害が出ています。
わずかな隙間でもシロアリにとっては
立派な侵入経路となります。
2010年07月14日
イエシロアリ
今日は非常に疲れました。
体力的にではなく精神的にです。
調査に行ったのですが、はたから見れば
ウロウロしたりボーっとしたりで変な人に見えたかもしれません。
でも頭の中はフル回転でした。
この時期はイエシロアリの現場がありますが
築年数の浅い物件は、家全体が発泡系断熱材に囲まれている状態です。
シロアリは木だけを食べるものと思っている方も多いですが
発泡系断熱材にシロアリが侵入すると性質が悪いです。
調査も一日がかりです。
調査の状況から駆除方法を考えるのですが
こんな現場では自作ノズルは何の役にも立ちません。
と言うよりもノズルに頼った仕事ではどうにもならないと感じさせられます。
駆除が完了するまでは考え込みそうです。
体力的にではなく精神的にです。
調査に行ったのですが、はたから見れば
ウロウロしたりボーっとしたりで変な人に見えたかもしれません。
でも頭の中はフル回転でした。
この時期はイエシロアリの現場がありますが
築年数の浅い物件は、家全体が発泡系断熱材に囲まれている状態です。
シロアリは木だけを食べるものと思っている方も多いですが
発泡系断熱材にシロアリが侵入すると性質が悪いです。
調査も一日がかりです。
調査の状況から駆除方法を考えるのですが
こんな現場では自作ノズルは何の役にも立ちません。
と言うよりもノズルに頼った仕事ではどうにもならないと感じさせられます。
駆除が完了するまでは考え込みそうです。
2010年06月17日
配管周り
新築時の配管立ち上がりです。
口の部分のテープはめくってはいけませんが
その他の部分は確認が必要です。
シロアリの侵入ルートが隠れています。
必ず侵入するかといえばそうとは言い切れませんが
下手なマニュアル式大量散布をするよりも
このような個所をしっかり押さえていく方が効果的です。
2010年06月09日
玄関付近のクラック
玄関ポーチと基礎立ち上がり部分です。
拡大すると境目は隙間があります。
玄関付近の羽アリの発生やドア枠などの被害で
床下はなんの被害もないという事があります。
知識のない業者では、直接羽アリが住み着いただの保証外だの言います。
しかしポーチ部分のちょっとした侵入ルートに気を配れば答えは簡単に出ます。
タイルやモルタルが張られても、基礎とは完全に一体にはなりませんので
クラックや浮きができてきます。
そこを利用して侵入し、玄関周りに被害を出していきます。
薬剤の種類や濃度を考えて使うのは当たり前ですが
特に新築時のコンクリートのアルカリ濃度が高いうちは尚更です。
2010年06月02日
施工の傷を減らす
玄関壁部分の写真です。
玄関が建物よりはみ出した構造ですので
この部分は床下から確認できません。
玄関は構造上、シロアリの被害が多い場所ですので
何かしらの対策がとられます。
しかし、無闇に穴をあけ薬剤を処理するのもスマートではありません。
この現場の場合、この位置から低圧で薬剤処理しましたが
4尺5寸(1.365m)先の土台と基礎の隙間にまで薬剤が浸み込みました。
すべての現場がこうなるとは限りませんが
マニュアル式に毎回同じ場所に穴をあけたりするのではなく
現場で状態をよく観察して、自作や特注の道具を使い
考えて施工すれば余分な傷(穴)は少なく出来ます。
2010年05月14日
業者の質
いつもお世話になっているハウスメーカーさんと電話をしていたところ、
築3年半の住宅で玄関ドア枠に被害、羽アリが出たとの話を聞きました。
施工を行った防蟻業者で対応してもらったところ
ドア枠は施工後に付けたものだから保証はできない、
また、昨年辺りに羽アリが飛んできて住み着いたものだろうと説明されたそうです。
あいた口がふさがりません・・・。
新築時にしっかりと状況を考えて薬剤や濃度を選択し、
マニュアル以外の場所に注意していれば結果は違ったでしょう。
そして羽アリが飛んできて1年程度でその状況がありえるのか、
そもそもペアリングして生き残るものがそうそういると思っているのか・・・。
その防蟻業者の質、モラルの無さに驚きます。
私からしてみれば明らかな施工ミスだと思うのですが・・・。
築3年半の住宅で玄関ドア枠に被害、羽アリが出たとの話を聞きました。
施工を行った防蟻業者で対応してもらったところ
ドア枠は施工後に付けたものだから保証はできない、
また、昨年辺りに羽アリが飛んできて住み着いたものだろうと説明されたそうです。
あいた口がふさがりません・・・。
新築時にしっかりと状況を考えて薬剤や濃度を選択し、
マニュアル以外の場所に注意していれば結果は違ったでしょう。
そして羽アリが飛んできて1年程度でその状況がありえるのか、
そもそもペアリングして生き残るものがそうそういると思っているのか・・・。
その防蟻業者の質、モラルの無さに驚きます。
私からしてみれば明らかな施工ミスだと思うのですが・・・。